「高齢者雇用が加速 70歳まで働ける企業が3割超に」
【現場に残る「制度の空隙」】
数字上は前進が見えても、現場では3つの空白が残っている。
① 就業機会は増えても、仕事の“質”が上がらない
再雇用で仕事内容や労働時間が縮小すると、生産性向上への貢献は限定的になる。
量だけ増えて質が伴わないというギャップがある。
② 学び直しの費用負担が曖昧
誰が費用を負担するのか不明確なままなので、
個人の可処分所得や時間の制約が障壁になる。
③ 健康・安全・ITスキルの壁
健康問題やITスキル不足が重なると、潜在的な早期離職を招きやすい。
➡ 「量」から「質」へ移すには、評価指標そのものが不足している。
🎓 教育・人材育成の現場からの声
しかし、教育の現場では次の課題が挙がる。
「短期講座はあるが、職務評価につながらない」
「修了証を取っても、賃金に反映されない」
一方で、日本の強みであるOJTは暗黙知に寄りがちで、
第三者評価で外部でも通用するスキルとして示す仕組みが弱い。
その結果、
→ 企業内に閉じたスキルは転職・兼業に展開できず、個人の学びの期待値を下げる。
→ これは 「人的資本の流動性」を損なう構造的問題。
🗾 地域格差と学びのハードル
さらに、地域差も大きい。
都市部:機会は多いが、時間単価が高く参加コストが重い
地方:そもそも講座が少なく、オンラインでも通信環境や学習支援が不足
一方で、高齢者のデジタル利用は進んでいるものの、
学習の継続率は年齢が上がるほど低下しやすい。
🎯 では何が必要か?
結論として、教育は「提供するだけ」では機能しない。
👉 重要なのは、学びを“伴走”し、かつ“評価・賃金につながる設計”を作ること。
それがなければ、
高齢就業を“質”で支える仕組みは育たない。
「70歳まで働ける企業が3割超」という事実は、人手不足の裏返しであると同時に、教育投資の不足を可視化する鏡でもある。(一次情報:厚労省発表内容に基づく報道より)
雇用の“延長”は、学びの“更新”が同時に起きて初めて、生産性の“上昇”へつながる。
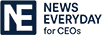

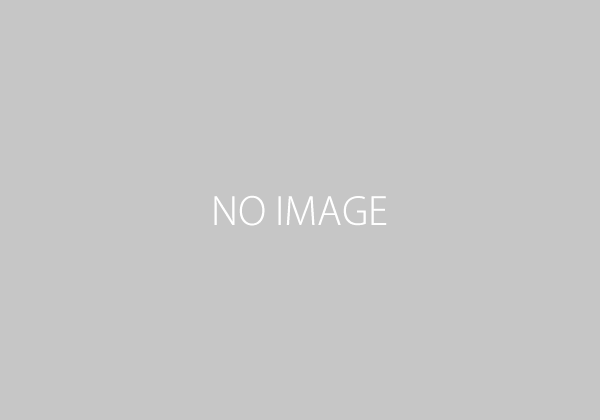


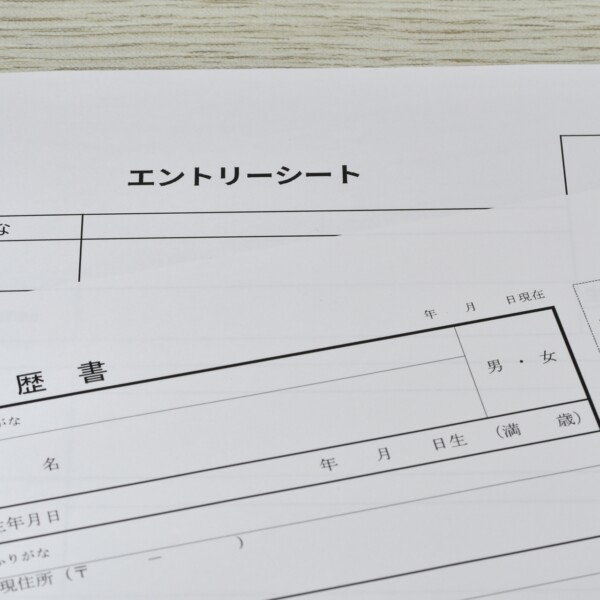



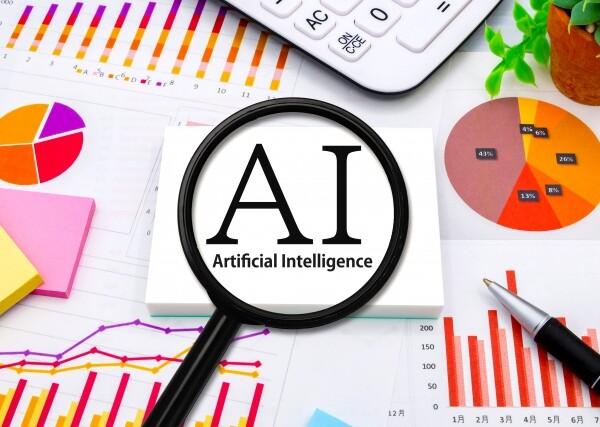






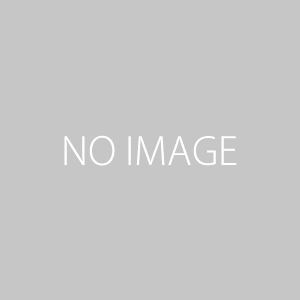





この記事へのコメントはありません。