「高齢者雇用が加速 70歳まで働ける企業が3割超に」
【10年後の日本は、、、?】

10年後には、70歳まで働く人が5割近くに増える可能性がある。
しかし、その中身は 「補助的な延命労働」 と 「価値を生む働き方」 の2つに分かれる。
価値を生む働き方にするには、
(1) 学び直しのモジュール化、(2) 賃金と職務の連結、(3) 安全・健康の確保、(4) EBPMによる継続的改善 が欠かせない。
つまり、学びと仕事の仕組みをつなぎ直すこと が核心だ。
また、労働力が不足するほど、教育投資の効果は高まる。
そして、可視化・標準化・連結 の3つが整えば、高齢就業は日本経済の柔軟性を底上げできる。
✔ マクロ経済の視点では
潜在成長率は、労働参加の増加で+0.1〜0.3ポイント押し上がる余地がある。
しかし、医療・介護需要の増加 や 生産性の伸び悩み が相殺要因となる。
そこで鍵になるのが、
「技能の載せ替え(再配置)をどれだけ早くできるか」 である。
AI・省力化投資と学び直しを同時に進め、シニアの役割を
「教える・標準化する・改善する」へ再設計 することが重要だ。
結論として、教育はコストではなくインフラ である。
これからは、公共投資と民間投資の最適な組み合わせをデータで探る時代 に入る。
【まとめ】
「70歳まで働ける企業3割超」は通過点に過ぎない。
一方で、大切なのは数字の背後にある人の物語を政策に翻訳することだ。
例えば、70歳の元係長のノートは、暗黙知を現場の共通財に変えた。
さらに、学びを可視化し、評価・賃金・働きやすさにつなげる仕組みを広げれば、こうした物語は特別でなくなる。
つまり、教育・人材育成は、長い就業時代の屋台骨である。
そして、データの限界や誤差も意思決定の材料に変えれば、数字に“温度”を持たせることができる。
(文・松永 渉)
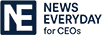

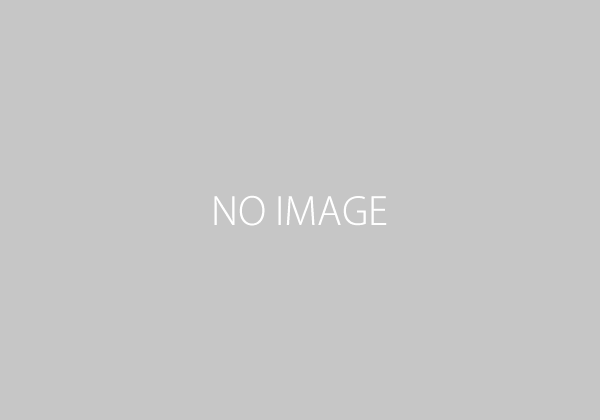


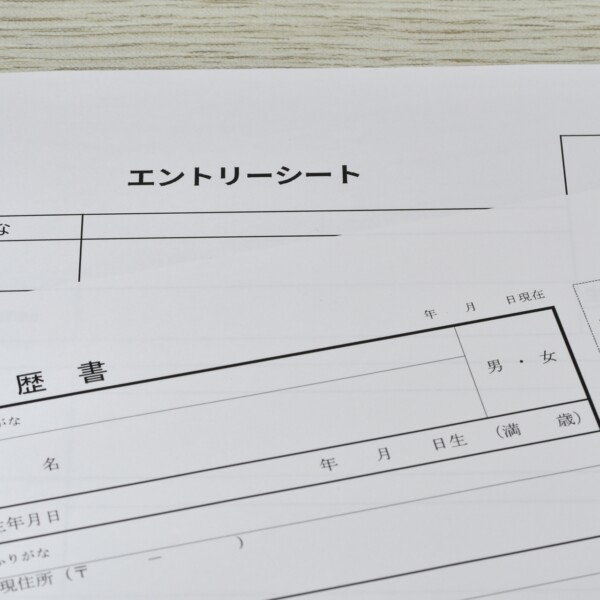



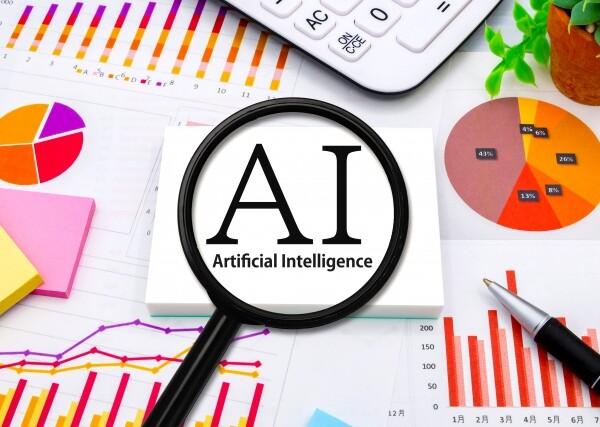








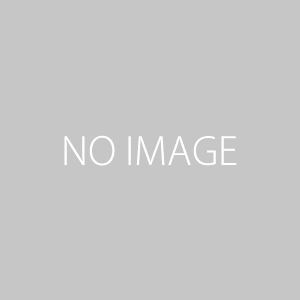



この記事へのコメントはありません。