
来春卒業予定大学生の内定率73.4%。安心の裏で進む「準備不足」と「ミスマッチ」を解きほぐす物語とデータ
現状分析:個人と企業のギャップ
「翻訳の欠如」が生む三つのギャップ
内定率が上がると、採用市場は「表面の安心」と「深層の課題」を同時に抱えます。いま顕在化しているギャップは大きく三つです。スキルの言語化不足、学習の可視化不足、制度の運用不足。いずれも“足りないのは才能ではなく翻訳”という共通点を持っています。翻訳とは、個人が持つ経験の価値を、企業の評価軸に合わせて伝えること。企業が持つ制度の趣旨を、現場の行動に落とし込むこと。翻訳が甘いほど、機会の取りこぼしが増え、選考や配属後のミスマッチが生まれます。
学生の経験が“事業価値”に変換されない理由
学生は日々、多くの経験をしています。アルバイト、ゼミ、サークル、ボランティア、ハッカソン、長期インターン。ところが、面接で「それは事業にどう効くの?」と聞かれると途端に言葉が詰まる。成果の数字化(何%改善したか)、再現性の説明(他社でも再現できる設計か)、意思決定の根拠(なぜその手を選んだか)。この三点が欠けがちです。企業側も、求める具体行動を明文化できていないケースが残ります。職種別採用を掲げながら、評価は総合職のままという矛盾も見られます。
学びは増えても“成果の証明”が追いつかない
MOOC、マイクロラーニング、ナノ学位。学習機会は豊富でも、履歴の統合と提示は未発達です。ポートフォリオは存在しても、職務記述書(ジョブディスクリプション)との対応関係が曖昧。企業は「学んだ」という申告より、「学びが成果に変わった証拠」を見たいのです。教育側がラーニングレコード(LRS)を活用し、成果物と評価を結びつけて提示できれば、採用の説得力は一段上がります。
制度はあるのに使われない組織のジレンマ
リモート、副業、フレックスを導入した企業は増えました。しかし、現場では「評価が不安」「申請が手間」「上司の理解がない」という理由で利用率が伸びないことが多い。制度は存在自体で価値を生まず、使われて初めて価値を生みます。利用データの公開、事例の横展開、評価制度の整合性、業務分解と成果指標の再設計。これらがそろって初めて、制度は「文化」に変わります。
「制度は書面では整っていました。でも、“安心して使っていい”という合図が現場に届いていなかった。人事がKPIに『利用率×満足度』を入れ、月次で共有し始めてから空気が変わりました」
人材開発マネジャー(教育・人材業)
才能より「翻訳」。制度より「運用」。今日できる最小の翻訳を始めよう。
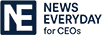

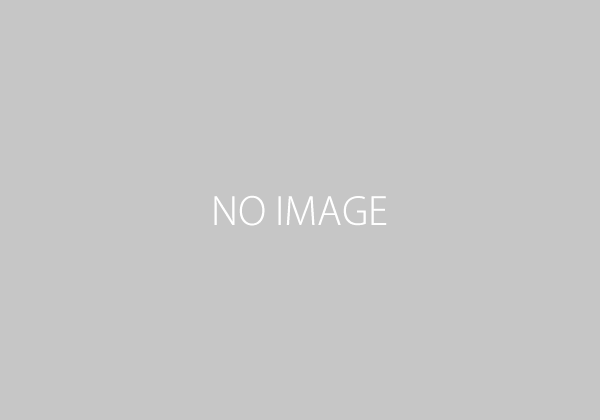


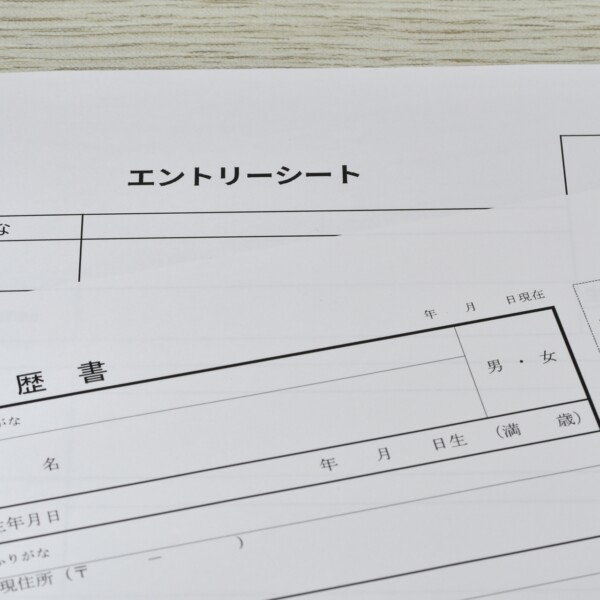



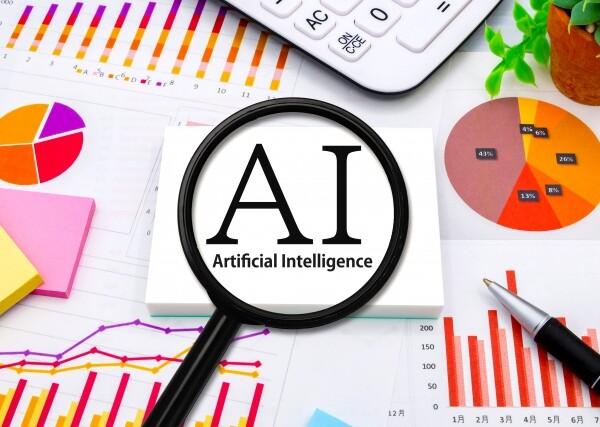








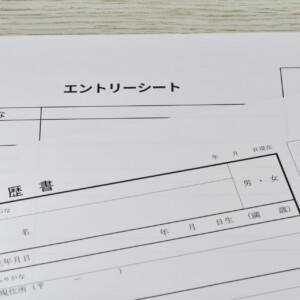

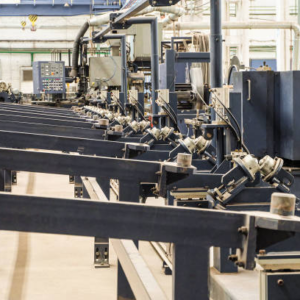

この記事へのコメントはありません。