
育児と仕事を両立するベビーシッター活用術|短時間サポートで心の余白をつくる実例と費用の考え方まで徹底解説
専門家と当事者の声
育児にも効く「ピンポイント支援」の知恵
福祉の現場にいると、家族の課題は「量」ではなく「タイミング」に宿ると感じます。負担の波が高くなる時間帯に、少しだけ人手があると、その日全体の印象が変わる。これは多くのご家庭で確かめられている日常の知恵です。看護・介護でも「ピンポイント支援」は有効とされます。育児も同じ。ベビーシッターの活用は、長時間の委託だけではありません。「寝かしつけ前の1時間」「保育園から帰宅直後の1.5時間」「朝の身支度の45分」。短いけれど、心の呼吸を取り戻す黄金の時間です。
活用の例A:在宅勤務の日の夕方90分
・保育園迎えと入浴の前後をサポート
・シッターは子の遊び見守り+洗い物
・親はオンライン会議に集中
・寝かしつけが穏やかになり、翌朝の気分が軽い
活用の例B:出張や遅番の日の朝45分
・登園準備と朝ごはんのサポート
・忘れ物チェックの余裕が生まれる
・兄弟それぞれのペースに合わせられる
・親子の会話が増え、送りの笑顔が戻る
完璧ではなく、風が通る家事と育児へ。
当事者の声も静かに増えています。「保育園の延長に間に合わない日は、帰宅後だけお願いしています」「子どもが『また遊びに来る?』と言ってくれて安心しました」「月2回の“自分の時間”で、夫婦の会話がやさしくなりました」。私の周りのママ・パパたちが、小さな活用から始めて、暮らしの景色を少しずつ塗り替えているのを感じます。みんながやっているからこそ、安心して試せる。社会的な背中押しは、心の疲れを溶かす春の陽光のようです。
ニュースから読み解く支援のいま
報道によれば、こども家庭庁は新たな経済対策に「ベビーシッター情報サイトの開設」を盛り込む方針です。親が安心して利用に踏み出せるよう、情報の集約と見通しのよさを高めるねらいがあるとされています。具体的には、サービスの探し方、利用時の留意点、各種支援制度の案内など、子育て世帯が知りたい「最初の地図」をまとめて示すことが想定されます。制度の詳細は今後の公表を待つ必要がありますが、「どこから始めればいいか」が見えること自体が、暮らしにとって大きな意味を持ちます。(出典:NHKニュース「ベビーシッター情報サイト開設 新経済対策に盛り込む こども相」)
「必要な情報に迷わず届く。そこから始まります」
子育て支援の現場より
私はこの動きを、「頼り合いの文化」に光が当たるサインだと受け止めています。ベビーシッターの活用は、都市部だけの話ではありません。情報がまとまれば、地域差の課題も少しずつ埋めやすくなる。さらに「誰かが使っている」「職場でも紹介された」「園からも案内があった」といった、社会的証明が広がると、個々の不安はやわらぎやすいとされます。大切なのは、使う・使わないの二択ではなく、「必要なときに選べる」という選択肢が手元にあること。雨の日だけ差す傘のように、持っているだけで心が落ち着く道具です。
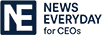

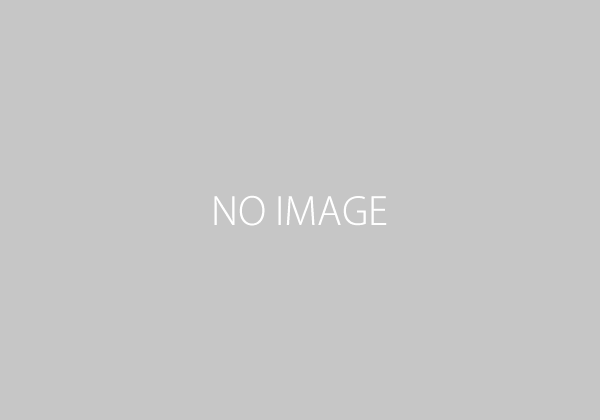


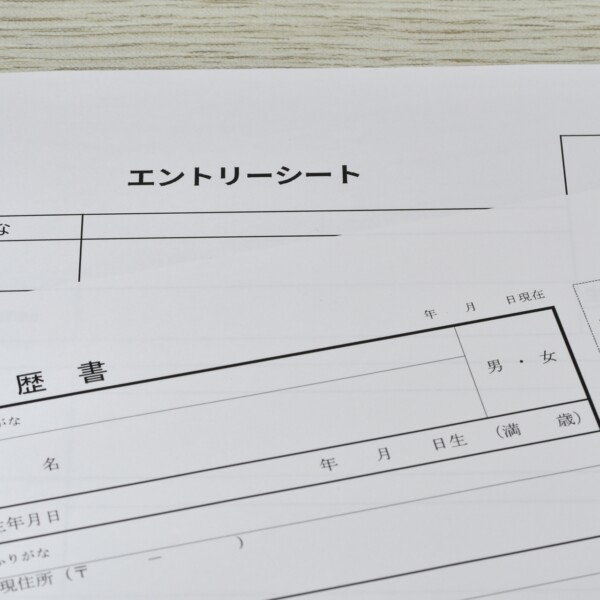



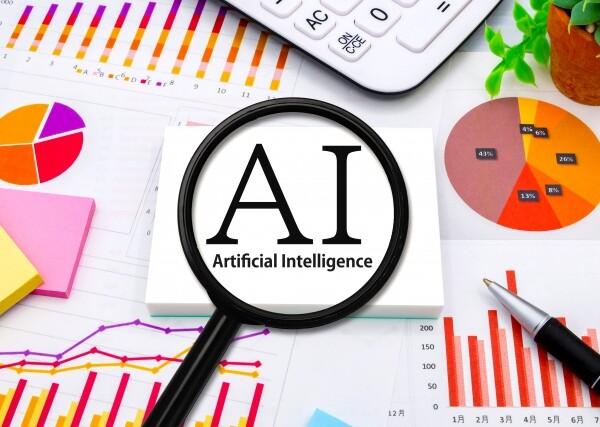













この記事へのコメントはありません。