
万博フレンチに学ぶ“選ばれる中小飲食店”──皿の上の伝承が売上とブランドを変える
家族という鏡

親と子の距離から、家族経営のブランドを考える
家族は、食文化のもっとも小さな学校だと感じます。親の手の癖、祖母の塩加減、日曜日の遅い昼食。家族経営の飲食店では、その学校がそのまま舞台になります。ある店のT氏は、父から受け継いだ中華鍋の重さを、初めて一人で振った日、「部屋の温度が1度上がったように感じた」と話してくれました。道具は体重と記憶を受け止めながら、持ち手に別の名前を足していきます。世代をまたぐと、重さは変わらないのに、意味だけが少しずつ変わっていきます。
「自分もそうだ」と感じる人は、実家の台所の匂いを思い出すかもしれません。油の匂い、味噌の湿度、冷蔵庫の扉の吸い付く音。そこにあるのは一種の「ブランド」であり、それは消費者のためというより、家族自身に効いているロゴマークのようなものです。朝の挨拶のしかた、食器のしまい方、失敗の受け止め方──それらすべてが、その家のブランドを編む糸になっています。店に来るお客様は、その糸目のしなやかさに安心し、ほどけにくさに信頼を寄せてくださっているのだと思います。
沈黙と対話のあいだに、経営のヒントがあります
継承の現場には、どうしても沈黙がつきまといます。「なぜその塩なのか」「なぜ今日は醤油を足したのか」。言葉を尽くせないのは、手の記憶のほうが早く動いてしまうからかもしれません。しかし沈黙だけが続くと、「正典」が硬くなってしまいます。対話は、硬くなった層に呼吸するための小さな穴を開けてくれます。若い世代の提案に、年長者の経験がうなずくとき、ブランドは弾力を取り戻します。私は、「わからない」と言える家族や店が、生き延びていくと信じています。
「料理は自然と文化の媒介である」
クロード・レヴィ=ストロース(意訳)
媒介には余白が必要です。過去をそのまま運ぶのではなく、過去の温度を測り直すことが大切です。たとえば、祖母のレシピの砂糖を一割減らしてみることもその一つです。その減らし方に宿るのは、時代の健康観だけではなく、今日の客層の顔ぶれや表情かもしれません。ボードリューが語る「社会化された選好」は、家族の内部にも存在しています。だからこそ、選好の地図を書き換えるたびに、家族は少しずつ「新しい自分」に近づいていくのだと思います。
こうした家族とブランドの関係は、NHKの他の人間ドラマ系コンテンツや、ビジネス系メディアでもたびたび取り上げられています。たとえば「老舗旅館の事業承継」などの事例記事は、飲食業の社長にとっても、「家族と経営をどう両立させるか」を考えるヒントになります。
















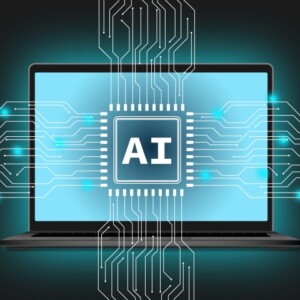




この記事へのコメントはありません。