
戦後80年とクリエイティブ業──中小企業のブランド戦略をどう変えるか
人の心に宿る揺らぎ

小さな違和感の正体
Kさんは、デザイン事務所でインターフェースの細部にこだわる人です。ある日、彼は「色が重たく見えるように感じます」とだけ言いました。数値上は問題のない配色でも、雨上がりの街で見たポスターの青が、彼の中で何かをわずかにずらしたのだといいます。「心の中で何かがずれた音がしました」と彼は笑いながら話します。ユングは、意識の下に広がる「無意識」を、個人の井戸と集合の地下水脈にたとえました。デザインの仕事もまた、その井戸から汲み上げた水を、社会にふさわしい器に注ぐ営みだと考えられます。違和感は、その器がまだ口を閉ざしている合図のように感じられます。
私たちの心は、天気図の等圧線のように、見えない差で輪郭を変えていきます。誰かの声色、過去の断片、未来の想像。そのすべてが、今日の判断に微かな風を起こします。アドラーは「共同体感覚」という言葉で、人が他者と結ばれるときの支えについて語りました。他者と結ばれているという実感は、違和感を「ただの不快感」ではなく、「注意深さ」へと変える力を持つのだと思います。Kさんは、その日の会議で「この青が、あの通りの濡れた石と合っていない気がします」と言い換えました。比喩の精度が上がると、会議室の沈黙は責める沈黙から、聴く沈黙へと変わっていきます。この変化は、そのまま「社内コミュニケーションの質」や「ブランド表現の精度」といった経営課題にもつながっていきます。
その痛みを言葉にするということ
痛みはしばしば、名付けられるまでのあいだ、身体のどこかにぼんやりと潜んでいます。デザイナーのT氏は、戦後80年の企画展の仕事を引き受けてから、夜の寝付きが浅くなったと話します。彼自身には戦争の直接的な記憶はありませんが、祖母の引き出しから出てきた手紙の匂いが、作業のたびに鼻の奥で蘇るのだといいます。「眠る前に、机の上で紙を撫でてしまいます」と彼は言います。その手つきは、誰かに触れているようにも見えました。ウィニコットが語る「ほどよい母」や「移行対象」の概念は、創作物が人の心の橋渡しを担う様子を思い出させてくれます。言葉にならない痛みは、触れるもの、見るもの、使うものへと移され、やがて語彙を獲得していきます。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは」
宮沢賢治『農民芸術概論綱要』
短い言葉は、ときに鋭く心を刺します。T氏は、展示の主役に何を置くのかを長く迷い続けました。写真なのか、音声なのか、あるいは無音の空間なのか。最終的に彼は、来場者の「手」を主役にすることを選びました。触れて初めて現れる文字、息をかけて浮かび上がる絵を中心に据えたのです。痛みを声にするとき、声の主を一人に固定しすぎない余白をどう設計するか。そこにこそ、彼の誠実さが宿っているように感じます。私たちも同じです。自分の声を出す勇気は、誰かのための余白を残す勇気とひとつながりだと感じる瞬間があるのではないでしょうか。
記憶は、触れた温度で形を変えます。温まったところから、言葉は芽吹きます。
こうした「痛み」と「記憶」の扱いは、戦後80年の文脈の中で進むさまざまな芸術・デザインの試みとも深くつながっています。たとえば、戦後80年と芸術表現をテーマにした展覧会では、アートを通じて原爆や戦争体験を次世代へ語り継ぐ試みが続いています。こうした外部の動きは、自社の企画展やブランドストーリーを考える際のヒントとしても、経営者にとって非常に参考になるはずです。

















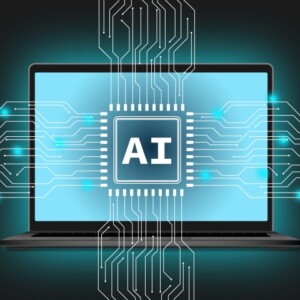



この記事へのコメントはありません。