
戦後80年とクリエイティブ業──中小企業のブランド戦略をどう変えるか
社会と文化の狭間で

個人と集団の境界
社会は、見えないインターフェースによって形作られているように感じます。法や制度という骨組みの上に、慣習や作法が筋肉のように重なり、さらに記憶や物語が肌の感覚を与えます。私たちクリエイティブ・デザイン業の仕事は、その「社会の肌」に触れる場面の多い仕事です。だからこそ、皮膚の厚みや温度差を知らないふりをすることはできません。ハンナ・アーレントは、人間の条件として「行為」を強調しました。集団の中で誰かの行為が「始まり」を生むという考え方です。個人の心が揺れる瞬間に、集団が少しずつ形を変えていきます。多くの経営者の方も、「それはたしかにそうだ」と感じるのではないでしょうか。心はいつも、境界で静かに震えています。
集団は、ときに個人の痛みを飲み込んでしまいます。あるプロジェクトの会議の終盤、ベテランの編集者が長く息を吐きました。彼は「ここにいる誰にも責任はないのですが、私には重く感じます」と静かに言いました。その「ですが」は、集団が生む無自覚と、個人が背負う自覚との間に引かれた細い線だったように思います。クリエイティブの現場は、スピードと効率の名のもとに、その線を見ないまま跨いでしまうことがあります。私はそれを責めたいのではありません。むしろ、その線を見えるようにすることこそが、文化やデザインの仕事の一部だと考えています。見えないものに、適切な明るさの光を当てること。それは、中小企業にとっての使命のひとつでもあるはずです。
文化が癒すもの/壊すもの
文化は、救いにも刃にもなります。戦後80年の歩みは、表現が人をつなぎながら、ときに深く傷つけてもきた歴史でもあります。NHKが伝えた音楽家の「覚悟」の言葉からは、その両義性をよく知っている眼差しが伝わってきます。語りすぎれば誰かの声を奪いかねず、黙りすぎれば誰かの痛みを増やしかねません。だからこそ、私たちは「光の角度」を学ぶ必要があります。文化は闇を消すことはできませんが、見える暗さへと変えることができます。デザインは、そこに座る椅子を置き、息の仕方をさりげなく提案できます。私は、企業のクリエイティブ部門がこの視点を持つことは、CSRやブランディングにおいても大きな価値になると感じています。
「見ることは関わることだ」
メルロ=ポンティ
見るという行為そのものが、対象の意味を変えていきます。戦後80年を記憶するプロジェクトに関わるとき、私たちは単に「観察」しているのではなく、強く「関与」しているのだと思います。そこには、企業のコンプライアンスや形式的なCSRの枠を超えた、日々の選択の重さが生まれます。書体ひとつ、余白ひとつに、受け取り手の呼吸をどれだけ思い描けたか。制作の手前で、誰の声を聴けたのか。私は、現場の会議に「呼吸を確かめる時間」を5分だけでも追加することを、経営者に提案したくなります。それは、コストではなく、長期的な信頼資本への投資だと考えられるからです。
そして、企業は問われます。「社会に何を残すのか」という問いです。戦後80年の節目において、それは豪壮な記念碑ではなく、日常の細やかな設計の中に宿ると私は感じます。たとえば、プロジェクトのアーカイブを「検索できる箱」ではなく、「語り直せる縁側」に変えていくこと。失敗の記録を、責める目録ではなく、学びの索引にしていくこと。社内の規範を、罰のリストではなく、ケアの手順書に近づけていくこと。こうした些細な更新が、やがて企業文化の体温になっていきます。以前の記事で扱ったCO2見える化義務化と中小企業のAI最短対策(※内部リンク:実際のURLに差し替えてください)でも、日常オペレーションの設計が長期的な信頼を左右することをお伝えしました。野田洋次郎さんが語った「自分にできること」という姿勢は、こうした企業という大きな身体にも、十分着地しうるものだと感じます。
同じように、戦後80年をテーマにした平和ポスターの取り組みでは、デザインの力を通じて平和への意思を可視化しようとする試みが続いています。これは、クリエイティブ・デザイン業に携わる中小企業が、自社のクライアントワークや自主企画の中で「社会的なメッセージ」と「ビジネス」をどのように両立させるかを考える上でも、示唆に富んだ事例だと言えます。

















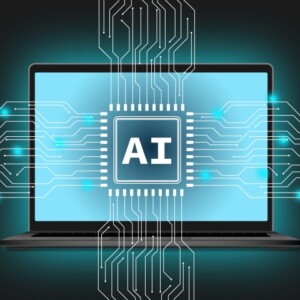



この記事へのコメントはありません。