
頂点への帰還――鹿島に学ぶ「停滞組織」を30日で立て直す社長の勝ち方
成功事例:あの日、彼らが掴んだ希望
あの日、切り替えは前線から始まりました。先制を許した直後、センターフォワードが自陣まで戻り、タックルでスローインを奪います。そこから10秒の間に、三人目の動きが連鎖し、左のアウトに転がしたボールがネットを揺らします。ベンチが、観客が、街が、同時に跳ね上がる瞬間です。目の前で、筆者は確信しました。「これは偶然ではありません」。トレーニングで反復した軌跡が、プレッシャーの中で自然に表出します。反射神経のように、チームが形を思い出します。大事なのは、正しい形を「体に入れておく」ことです。

「緊張していました。でも、約束したことをやればいいと思いました。前に走る、背後を取る、戻る。僕たちは毎日、それを練習してきました」
20代前半のウイング
監督の介入は、最小で最大です。ハーフタイムにホワイトボードへ描かれたのは、たった三本の矢印でした。矢印の角度は数度、距離は五メートルだけ伸ばし、背後を直線で刺します。それだけで、相手のラインは崩れます。ビルドアップの第一歩をずらし、奪いどころを一点に集約します。複雑な戦術書を編むよりも、現場で通る言葉を磨くことに集中します。小さく、わかりやすく、実行できる。このナレッジは、地方の中小企業やクリエイティブ・デザイン業のチーム運営にもすぐに持ち込める経営ノウハウです。
勝利は、たった一歩の「できた」を積み重ねた副産物です。
終盤、勝ち切るための勇気が問われました。交代枠の使い方に迷いはありません。足の止まったサイドに、走れる選手を投入します。守るためではなく、ボールを前へ運び切るための交代です。追加点は生まれませんでしたが、ボールは前で死にました。時間の砂は確かに落ちていますが、砂時計を倒すようなプレーがあります。コーナーへ運び、ファウルをもらい、相手の体力を削ります。誰もが役割を理解し、最後の1メートルを走り切ります。肩で呼吸する彼らの横で、筆者はペンを握る手を一度止めました。「人は、ここまで強くなれるのだ」と。
こうした「勝ち切る技術」は、例えば「残業時間を増やさずに売上を伸ばす経営」にも通じます。中小企業の社長にとってのゴールは、単に目先の数字を守ることではなく、社員と会社の両方が「明日も走れる状態」を維持することです。その視点で試合を見直すと、鹿島の再生はビジネスの実践書としても読むことができます。



















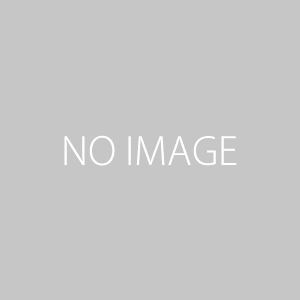

この記事へのコメントはありません。