
縮小の美学——三省堂書店「神田神保町本店」が映す”小売業の持続可能な経営”
【目次】
心の風景と社会の断片
雨が上がった舗道に、遅れて降りてくる光がある。濡れたアスファルトは鏡のように街を逆さに映し、通りすがる人の声はひそやかに溶けていく。古書の街で、閉じた扉の前に立つ私の手は、見えない鍵を探して宙をまさぐる。紙の匂いは記憶の深い井戸から立ちのぼり、失ったものの輪郭を、ゆっくりと浮かび上がらせる。いつからだろう、店が小さくなるというニュースを、胸のどこかで自分のことのように受け取るようになったのは。縮むという言葉は冷たく硬いが、その響きの奥には、守りたいものの温度が潜んでいるようにも感じる。
「三省堂書店・神田神保町本店」という名に、「神田」を重ねる。古い地図の余白に鉛筆で文字を継ぎ足すような仕草だ。光は斜めに差し、看板の金属に短い午後を刻む。歩けば、世界がひろがる——そう掲げられた言葉の前で、私たちは足の運びを確かめる。売り場が4割ほど少なくなると聞いて、部屋の温度が1度下がった気がした。けれどその分、棚と棚のあいだに生まれる静かな間は、迷いと出会いのための余白になるのかもしれない。
心の中で、何かがずれた音がした。薄い木の板がきしむような微かな音だ。失うことを嫌う心は、日々の小さな変化にも敏感で、上着のポケットに入れた鍵が少し軽くなっただけでも、胸の奥のほうで鈴が鳴る。私もそうだ。売り場が減ると聞けば、出会えたはずの本が消える気がして息を潜めてしまう。けれど、その音は、別の可能性に振り向く合図でもあるのだろう。捨てるのではなく、選び直す。減らすのではなく、響かせる。
記憶は、声のない図書館のようだ。棚に並ぶ背表紙は、自分がかつて選ばなかった道でできている。雨上がりの匂いが運んでくるのは、あの日手にとって戻した一冊のひやりとした触感。私もそうだ、と誰かがつぶやく。心の表面を撫でる風の温度は、過去と未来のあわいで少し揺れている。損ないたくないものを抱きしめるほど、腕の中で息苦しくなるのはなぜだろう。きっと、守るとは形を変えることだと、どこかで知っているからだ。
夕方の光は低く、窓辺で折り紙の影を長く伸ばす。街のざわめきの粒子が小さくなり、一冊の本に落ちる視線の重さが確かになる。ここに、縮小の美学があるのだと私は思う人もいるだろう。たとえば器は小さいほうが香りが立つように、限られた空間が混沌をほどき、選び抜かれた背表紙の連鎖が、私たちの歩みに細い道標を灯す。心は、広場よりも懐に似ている。狭いが深い、近いが遠い。その相反のなかに、失わない道が見え隠れする。
夜が来る前の短い時間、街は呼吸を整える。喫茶店から漏れる声の温度、カップの縁に残る光の輪。記憶はそこに座り、過ぎたページをそっと撫でる。私は自分に言い聞かせる。小さくなることは、弱くなることと同義ではない。むしろ、私たちの生活は縮小を通して輪郭を取り戻すことがある、と。私もそうだ。持ち物を減らした部屋で、音楽が少し良く聴こえた夜を、いまも覚えている。縮むとは、選ぶこと。選ぶとは、誰かの声を大切にすること。その誰かに、未来の自分も含めて。




















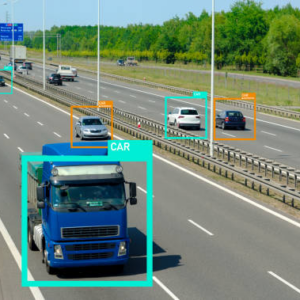



この記事へのコメントはありません。