「高齢者雇用が加速 70歳まで働ける企業が3割超に」
厚労省が公表した「70歳まで働ける企業が3割超」という事実は、単なる高齢化の副産物ではない。教育・人材育成の設計を変えれば、生産性と包摂を両立できる。数字が物語る現実から、政策の針路を示す。
【目次】
- 数字が語る社会のリアル
- 現場に残る「制度の空隙」
- データで見る課題の構造
- 国内外の比較事例
- 10年後の日本を予測する
- まとめ

【数字が語る社会のリアル】
定年の鐘が鳴っても、仕事は終わらない。
地方の製造現場では、70歳の元係長が週3日で後進を支え、技術を“見える化”して生産性を上げている。
彼が作った手順書や図解は、歩留まりを数%改善し、若手の残業も減らした。
高齢者の就業は“感傷”ではなく、現場の設計そのものを変える力を持つ。
📊 日本の現状:労働の「時間軸」が伸びている
・出生率は約1.2、団塊世代は後期高齢期に入り、労働力不足が深刻化。
・製造・サービス・介護など多くの業種で人が足りない。
・その結果、働く年齢の上限が“自然と”引き上げられている。
つまり、
70歳まで働ける企業が3割を超えたのは、社会構造の変化による“必然”でもある。
🏢 企業の動き:出口(就業の終わり方)だけが広がる
企業は以下のような制度を広げている:
・再雇用の延長(70歳まで)
・定年制の廃止
・業務委託としての活用
ただし、問題もある。
「入口(教育)」と「途中(スキル更新)」の仕組みが追いついていない。
学び直しの環境が弱いと、
長く働くことが 負担や疲労 になってしまう。
🎓 なぜ教育が重要なのか?
・中高年のスキル更新が遅れると、技術や知識が世代間で断絶する
・暗黙知は放っておいても継承されない
・AI・自動化が進むほど、非定型の判断力・コミュニケーション力の重要性は増す
・だからこそ
「測れる学び」をつくり、評価 → 賃金 → 働き方につなぐ仕組み
が不可欠
🔢 核心の数字(大切なので太字)
・70歳まで働ける企業:3割超(厚労省)
・65〜69歳の就業率:約5割(総務省)
・有効求人倍率:1.25〜1.30のレンジ(人手不足が慢性化)
・これらは、
高齢就業が「労働力不足の対応」と「技能の再配置」の両面で重要になっている
ことを示す。
🧩 本当に問われていること
多くの高齢者は再雇用で働き、
賃金はピークの6〜7割に下がるが、それ自体は問題ではない。
本質は、
・中高年の学びや技能を、どう賃金・評価・働き方に接続するか?
・中高年の学びを“見える化”して認証する
・企業内だけでなく、外部の短期講座や資格とつなぐ
・現場で価値を生むスキルを、正当に評価する回路を太くする
これができなければ、
70歳就業の「3割」は天井のままになる。
逆に整えば、基礎ラインとして拡大していく。
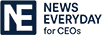

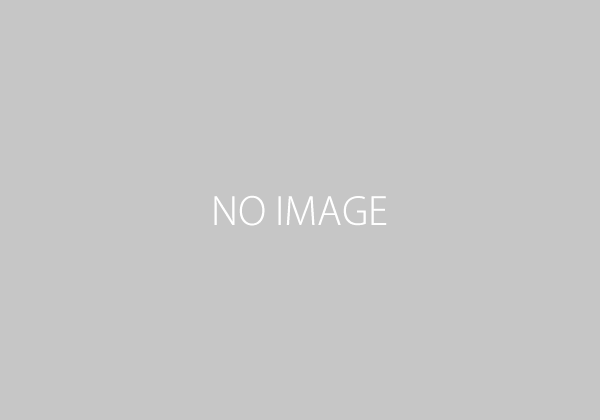


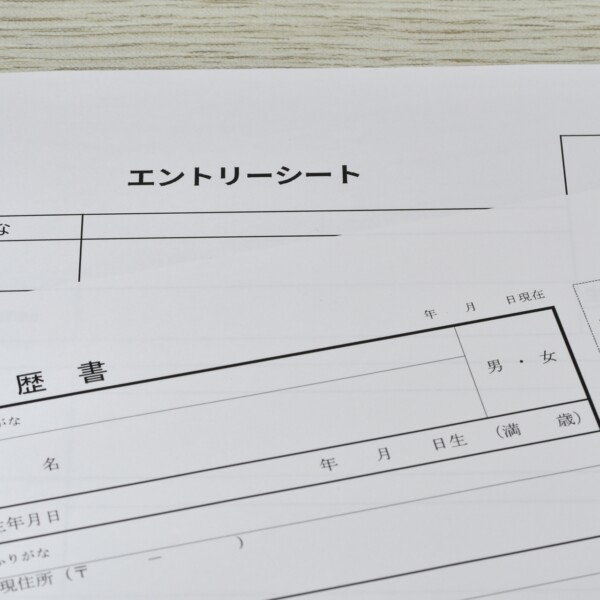



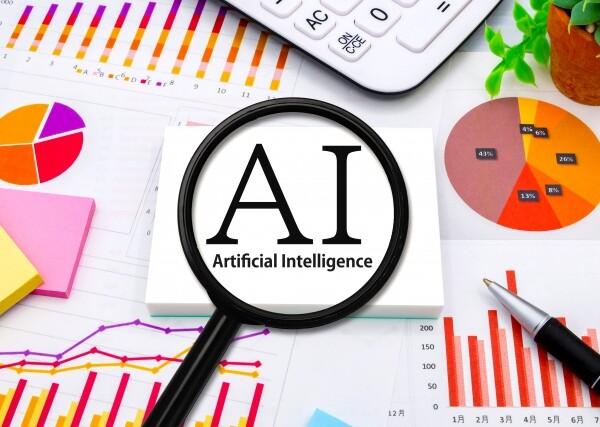





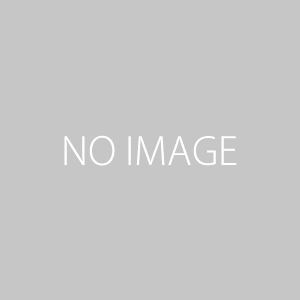







この記事へのコメントはありません。